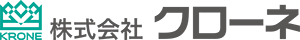温度校正器の精度と不確かさについて2024.6.19

経験の浅いユーザーによっては、精度と測定の不確かさの間に重要な違いがあることを知らないということが多々あります。この記事では、SIKAの温度校正器(Premiumモデル)における精度の定義と、不確かさの違いを説明します。
真の温度と校正器の温度との差とは
温度校正器の精度は、実際の温度と校正器が生成する温度との誤差を表します。
簡単な例を挙げましょう:
100.000℃に設定した校正器の中に100.005℃を示す標準温度計があります。
校正器の機器精度(スペック)は±0.070℃とします。
これは、校正器の全温度範囲にわたって、真の温度から±0.070℃の誤差が許容されることを意味します。したがって、校正器が100.000℃を示す場合、標準温度計の値は99.930~100.070℃でなければなりません。上記の例では、このように標準温度計の値は校正器の許容誤差(精度)内に正確に収まっています。
しかし、この例で使用した標準温度計にも測定誤差があります。また、ドリフトもありますし、標準温度計に接続されている測定ブリッジにも測定誤差があります。
その結果、精度は単に標準温度計からの誤差ではなく、真の温度からの誤差となります。したがって、SIKAが指定する精度には、真の温度と校正器に表示される温度との間に"誤差を生じさせるすべての要因"が含まれています。
ここで示す「誤差を生じさせる全ての要因」とは以下の通りです:
• ブロックと校正インサート間の温度差の再現性(内部基準センサーを使用した場合のみ該当)
• 基準センサーの再現性
• 基準センサーの長期ドリフト(12ヶ月間)
• 標準温度計の測定の不確かさ
• 標準温度計の測定ブリッジの測定の不確かさ
• 校正器の直線性エラー
これらの要因をすべて考慮すると、この例では、全温度範囲にわたって±0.070℃の精度(真の温度と校正器の温度との差)を確認することができます。
不確かさのさらなる要因
一方、温度校正器の測定の不確かさを知りたい場合は、さらなる要因が絡んできます:
• 校正器はどの程度温度を安定させることができるのか?
• 複数のセンサーを同時に校正器に接続した場合の影響は?
• 校正インサートの孔間の温度差
• 校正インサートへの校正対象センサ挿入長(深さ)の違い
一言で言えば 測定の不確かさには、測定誤差に関連する追加要因が含まれ、測定の不確かさに影響を与えるすべての要因を考慮した上で、校正器がどの程度正確に動作できるかを示します。
不確かさに関する詳しい説明
公式ガイドラインDKD-R 5-4に準拠した測定の不確かさに関する詳しい説明は、こちらに記載されています。